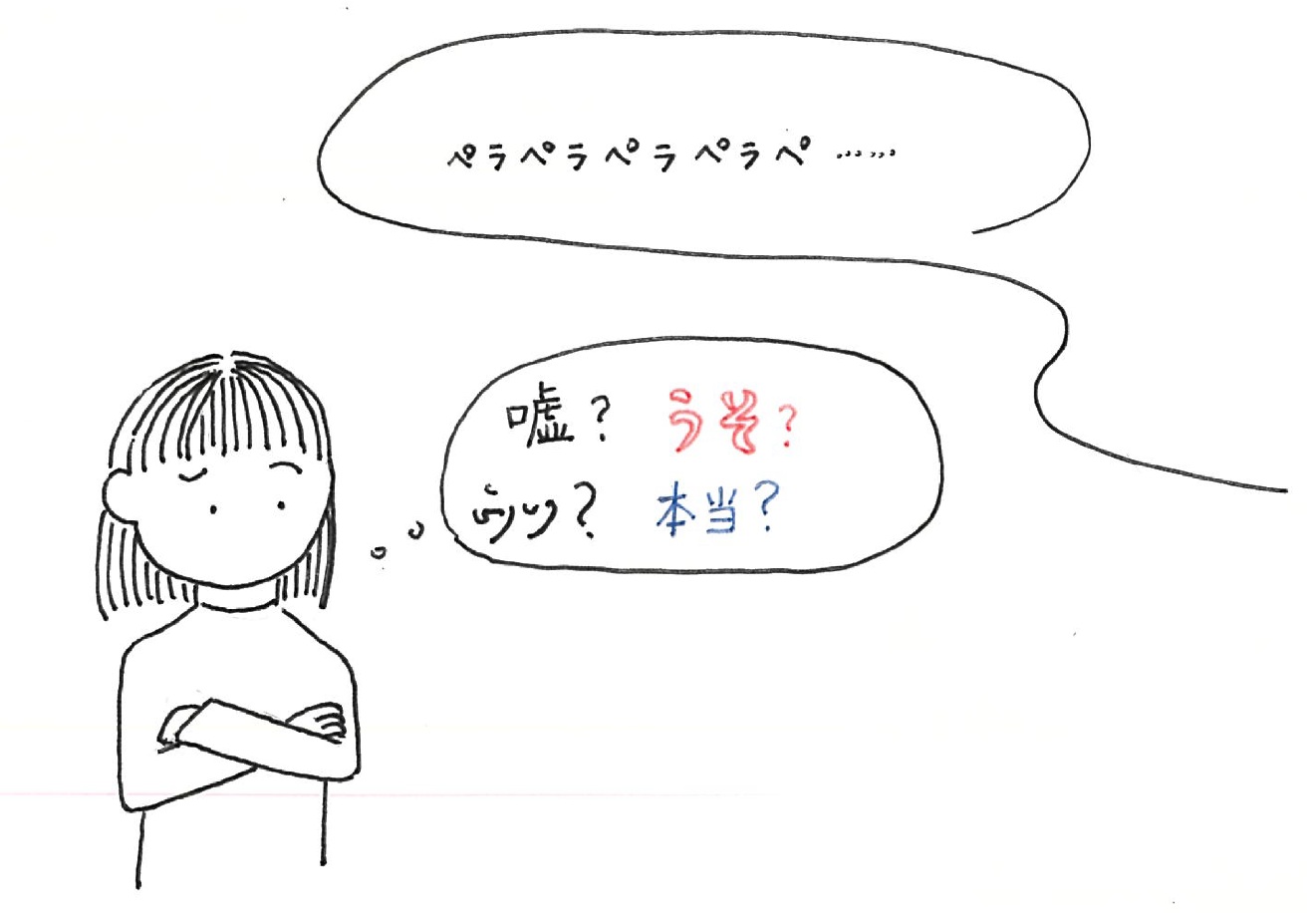体が溶けてしまいそうなくらい暑い日々も終わりを迎え、ようやく過ごしやすい日々が増えてきました。朝、空を見上げると雲がとても高い位置に移動していて、秋になった実感が湧きます。
いろいろな「○○の秋」がありますが、皆さんはどのような秋を過ごしていらっしゃるのでしょうか。通勤時間が長い私は「今年こそは読書の秋に!」と思いつつ、結局電車の中では寝てしまうということを毎年繰り返しています。
「食欲の秋」はよく聞きますね。コンビニやスーパーのお菓子コーナーでは、これはまた美味しそうなパッケージの商品が並び、仕事で疲れた時のため…と、お菓子をついつい買ってしまいます。
昔からあるお菓子の中で、動物の名前が英語で書いてあるものがありますね。きっと召し上がったことのある方も多いと思います。実は、珍しい動物も紹介されているのはご存知でしょうか。
monkey(猿)
polar bear(ホッキョクグマ)
lynx(オオヤマネコ)
rabbit(兎)
peafowl(孔雀)…
オオヤマネコ(lynx)は初めて目にしました。さらに孔雀のpeafowl。孔雀ってpeacockじゃないの? と疑問に思い調べてみると、雄の孔雀がpeacock、雌がpeahen、区別せずに一般的に孔雀を指す場合がpeafowlでした。
英語では孔雀のように、雄・雌・子どもで呼び方を変える動物が多くいます。例えばライオンは、雄=lion/雌=lioness/子ども=cub。cubは割と広く使われていて、ライオン以外にもキツネやトラ、熊の子どももcubと言います。
ほかにもどんなものがあるか、クイズ形式でご紹介します。超難問ですが、ヒントを読めば意外と簡単かもしれません。ぜひチャレンジしてみてください。
| | 雄 | 雌 | 子ども |
| cat(ネコ) | 1 | queen | kitten |
| chicken(鶏) | 2 | hen | chick |
| horse(馬) | 3 | mare | foal |
| sheep(羊) | ram | ewe | 4 |
| pig(豚) | boar | sow | 5 |
1のヒント:アニメ『〇〇とジェリー』でジェリーを追いかけるのが雄猫。
2のヒント:ブルースの名曲“Little Red 〇〇”の〇〇は雄鶏。
3のヒント:〇〇は優秀な雄の競走馬。
4のヒント:シチューに入れる〇〇肉は子羊の肉。
5のヒント:プーさんのお友達の子豚の名前は〇〇。
答えはイラストの下です。
答え:
1.tom
2.rooster
3.stallion
4.lamb
5.piglet
それでは皆様、素晴らしい秋をお過ごしくださいませ。
〈英語担当T〉
#英語 #動物の名前 #クイズ #秋 #食欲の秋
「赤」と聞くと何を思い浮かべますか。一般的には「情熱」「緊急」「太陽」などエネルギーを感じられるものが多いのではないでしょうか。編集の仕事をしていると「赤」はもっぱら「赤字」。たくさん書かれるとげんなりします。
色が組み合わさって新たなイメージを生むこともありますね。 例えば「赤」と「白」だと「おめでたい」。英語でも他の語と組み合わさって特別な意味を表す色があります。
Every moment, red letter
こちらはディズニー映画『アラジン』のA Whole New Worldの歌詞の一部です。A Whole New Worldを歌うシーンといえば、アラジンとジャスミンが魔法の絨毯に乗って飛び回る、あの壮大で美しいシーンです。
「こんな歌詞あったかな?」と思う方もいらっしゃると思います。英語でかつ掛け合いの部分なので、分かった方はかなりのディズニー通ですね。この歌詞、every moment=一瞬一瞬/red=赤い/letter=手紙、と脳内変換するとどうもあのシーンにそぐわない意味になってしまいます。
私が小さい頃、手紙は赤で書いてはいけないと言われました。古い考えなのかもしれませんが「赤いペンで書く手紙は絶交」を意味するからです。幸い、これまで赤いペンで手紙を書いたり、そんな手紙をもらったりしたことはありませんが、「Tさんへ」と赤字のメモをもらうと毎回ちょっとドキッとします。
ちょっと脱線しましたが、この歌詞のポイントはletterの意味です。このletterは「手紙」ではなく「文字」。赤い文字はどこで見るでしょう? 会社でも家でも毎日1回は目にしているはずです。そう、カレンダー! カレンダーで赤字になっている日は、祝日などの大切な日ですね。このことから、英語ではいつまでも覚えておきたい大切な日をred-letter dayと言います。
つまり、歌詞で言っているのは、アラジンとジャスミンが会っている時間は一瞬一瞬が大切な、忘れられない時間ということです。絶交しなくてよかった。めでたし、めでたし。
白も特別な意味を持つときがあります。
a white lie to protect the bigger truth
直訳すると「白い嘘」。なんだかピンときませんが、white lieとは「たわいもない嘘」「相手を傷つけないための嘘」を指します。blackの反対のwhiteにはpure(純粋)、さらにgoodやright(よい、正しい)、といったイメージがあるので、礼儀的な嘘といった意味になったのだと思います。上の英語は「もっと大事な真実を守るためについた、たわいもない嘘」といった感じでしょうか。
日本語だと「白い嘘」はないですが、「真っ赤な嘘」はありますね。これはどういう理屈なのでしょうか。国語科担当に聞いてみました。
・・・・・
日本語の「赤」という言葉には、接頭語として名詞につき、「全くの」「明らかな」という意味を表す用法があります。「赤の他人」「赤恥」などと使います。「真っ赤な嘘」は、ここから派生して、さらに意味を強めた「ごまかしがきかないほど明らかな○○」という意味になるのです。「真っ赤な嘘」というのは「疑いようもなく完全に嘘!」ということですね。
―国語科担当Oさん
・・・・・
同じ色でも、文化が違うと意味も全く異なるのが言語のおもしろいところですね。
次回もお楽しみに!
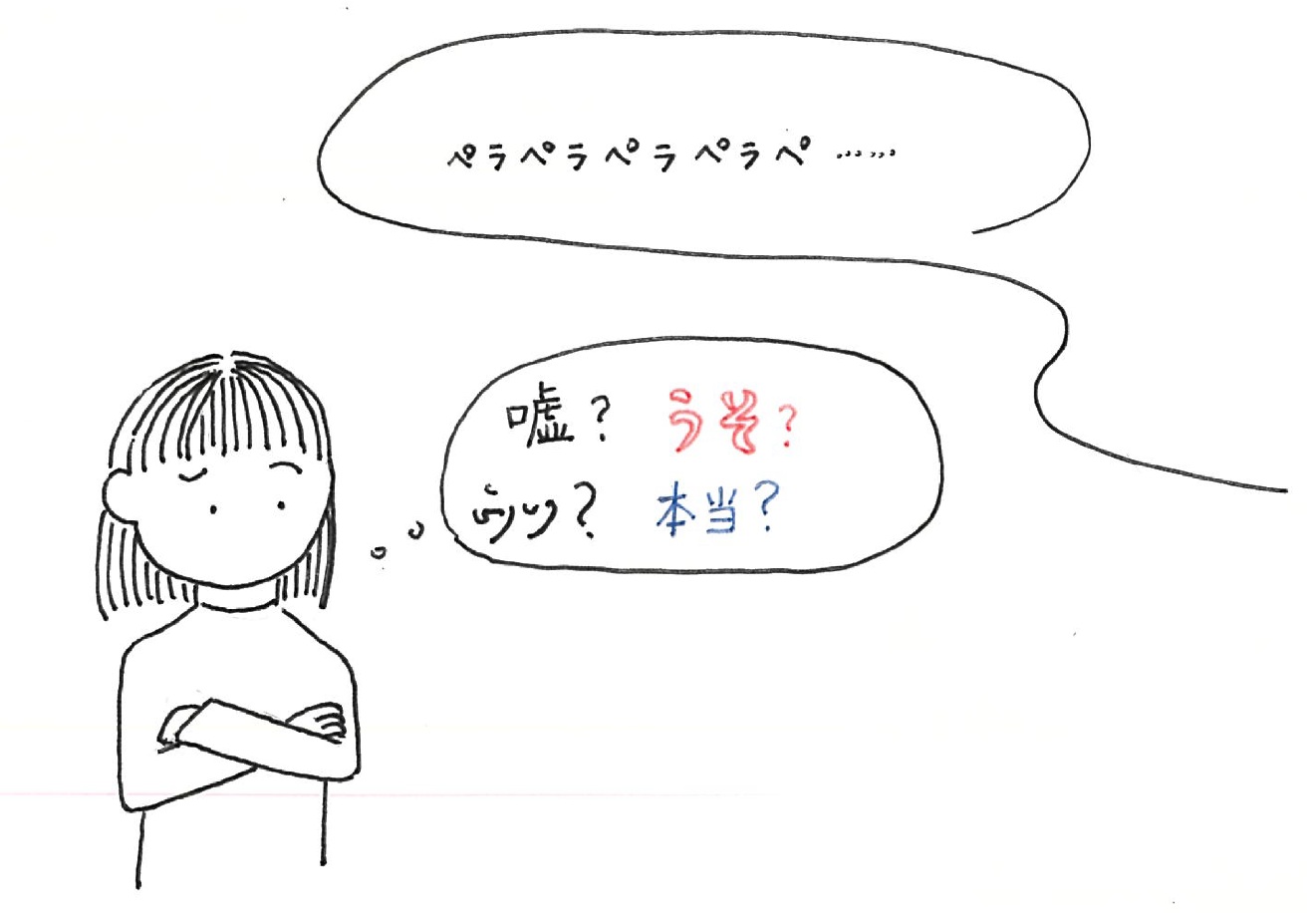
〈英語科担当T〉
#国語 #英語 #英語の歌詞 #英語の色
どんな仕事にも、始まりがあります。
それが“編集者”という職業であっても、きっと「最初の誰か」がいたはず。
では、その“元祖編集者”とは一体誰なのか?
ふと気になって、ChatGPTにたずねてみたところ──
アリストファネス(紀元前257年ごろ〜)という人物が挙がってきました。
(『女の平和』のアリストファネスとは別ですね。)
古代アレクサンドリア図書館の学者で、『ホメロス』などの古典作品を整理・校訂し、
なんと句読点(の原型)まで考案したという、まさに“読点の父”。
「本を読みやすく整える」という行為を、初めて職能として担った人の一人とされているそうです。
驚くべきはその時代。約2300年前です。
もしこの説が正しければ、私たち現代の編集者は、気が遠くなるほどの系譜の末端にいることになりますね。
そんな壮大な話に思いを馳せつつ──
2025年、私たちにもっと身近な“先輩編集者”にも注目が集まっています。
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公、蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)、通称「蔦重(つたじゅう)」。
江戸の出版文化を牽引した人物であり、編集者であり、プロデューサーであり、
ひとことで言えば、江戸“カルチャー”の仕掛け人。
その情熱と行動力には、現代の出版人も思わずうなるはずです。
実は昨年、蔦重にまつわる自治体の小冊子の制作に関わらせていただく機会がありました。
歴史に名を残す先輩の仕事に触れるような思いで、身の引き締まる経験でした。
ドラマはまもなく折り返し地点。
まだ追いつけます。編集者の目線で見てみるのも一興です。ぜひ、ご覧になってみてください。
〈一般書担当I〉